トランプ政権一期目での関税政策の推移
2017年:方針表明と初期の動き
- 1月23日: トランプが就任早々にTPP(環太平洋パートナーシップ協定)からの離脱を表明。多国間貿易協定を見直し、二国間交渉を重視する方針を示す。
- 通年: 具体的な関税発動は少なかったが、NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉開始(8月)や中国の貿易慣行に対する調査(通商法301条に基づく、8月)を進め、保護主義の基盤を構築。
- 影響: この年は関税よりも政策の方向性を打ち出す準備期間。市場はトランプの強硬姿勢に警戒しつつも、大きな動きは翌年に持ち越し。
2018年:関税政策の本格化
- 1月23日: 太陽光パネルと洗濯機にセーフガード関税を発動。太陽光パネルは30%(初年、以降逓減)、洗濯機は20~50%(輸入量に応じて)。中国や韓国が主な標的。
- 3月8日: 通商拡大法232条に基づき、鉄鋼25%、アルミニウム10%の関税を全世界に課すと発表。国家安全保障を理由に正当化。
- 3月23日発動: カナダ、メキシコ、EUなどは当初除外されたが、交渉の進展次第で適用対象に(例: カナダ・メキシコは2019年まで除外)。
- 報復: EU、中国、カナダが報復関税を表明(例: EUは米国産ウィスキーやハーレーダビッドソンに報復)。
- 4月3日: 通商法301条に基づき、中国製品500億ドル相当に25%関税を提案。知的財産権侵害への対抗措置。
- 7月6日: 第1弾として340億ドル分発動。
- 8月23日: 追加で160億ドル分発動。中国も同規模の報復関税を実施。
- 9月17日: 中国製品2000億ドル相当に10%関税を発表(9月24日発動)。2019年1月に25%へ引き上げ予定と警告。
- 影響: 米中貿易戦争が本格化し、株価や為替市場が不安定に。米国企業はコスト増に直面。
2019年:貿易戦争の激化と交渉
- 5月5日: トランプが2000億ドル分の関税を10%から25%に引き上げるとツイート(5月10日発動)。米中交渉の停滞が背景。
- 6月29日: G20大阪サミットで米中首脳会談。追加関税(3000億ドル分)を一時凍結し、交渉再開を合意。
- 8月1日: 交渉決裂を受け、3000億ドル分の中国製品に10%関税を課すと発表(9月1日と12月15日に分割発動)。
- 12月13日: 「第1段階合意」に到達。中国が農産物購入を増やす見返りに、一部関税(3000億ドル分のうち1200億ドル分)を15%から7.5%に引き下げ、残りの追加関税を凍結。
- 影響: 関税拡大で米消費者物価が上昇(例: 洗濯機価格は34%増)。一方、年末の合意で市場は一時安定。
2020年:コロナ禍と関税の小康状態
- 1月15日: 米中が第1段階貿易合意に署名。中国は米国産農産物・エネルギーを購入拡大。関税は現状維持で追加措置なし。
- 3月~: 新型コロナウイルスのパンデミックで経済が混乱。関税政策は後退し、緊急経済対策(CARES法など)に注力。
- 5月17日: カナダ・メキシコへの鉄鋼・アルミ関税を撤廃(2019年5月に合意済み)。USMCA(新NAFTA)が7月1日に発効。
- 影響: コロナ禍で貿易戦争は一時休戦状態に。関税よりもサプライチェーン混乱や景気対策が優先。
総括
- 2017年: 関税政策の準備と方針表明。
- 2018年: 鉄鋼・アルミ関税と米中貿易戦争の開始。
- 2019年: 関税のエスカレーションと第1段階合意による緊張緩和。
- 2020年: コロナ禍で関税政策が停滞、USMCA発効。
1. 株価の推移
トランプ1期目は、米国の経済政策(減税、規制緩和、貿易戦争など)が日本企業、特に輸出依存度の高い自動車メーカーの株価に影響を与えました。
トヨタ自動車 (7203)
- 2017年: トランプ就任時(2017年1月)の株価は約6,500円前後。減税期待や米国経済の好調さで、2017年末には7,000円台に上昇。
- 2018年: 米中貿易戦争の影響でボラティリティが増し、6,000~7,500円のレンジで推移。年末は6,500円程度に下落。
- 2019年: 米国の利下げや経済安定で回復し、7,000~8,000円台に。年末は約7,800円。
- 2020年: コロナ禍で3月には5,500円まで急落したが、財政・金融支援で急速に回復。年末は7,900円前後。
- 総括: 期間中のピークは2019年末の約8,000円、底値は2020年3月の5,500円。トランプ政策への期待と不安が混在しつつ、全体では上昇傾向。
ホンダ (7267)
- 2017年: 就任時は約3,200円。トヨタ同様、初期の楽観論で3,500円台に上昇。
- 2018年: 貿易摩擦で3,000~3,600円のレンジ。年末は2,900円程度に下落。
- 2019年: 緩和的な金融環境で3,000~3,300円で安定。年末は3,200円前後。
- 2020年: コロナショックで2,200円まで下落後、回復し、年末は2,800円程度。
- 総括: ピークは2017年の3,600円台、底値は2020年3月の2,200円。トヨタより変動が大きく、回復も緩やか。
比較: トヨタは堅調なブランド力と多角化で株価が比較的安定。ホンダは北米依存度の高さから、貿易政策やコロナの影響を強く受けた。
2. 業績(売上高・営業利益)
業績は各社の年度決算(トヨタ・ホンダともに3月期)に基づきます。
トヨタ自動車
- 2016年度(2016.4~2017.3): 売上高27.6兆円、営業利益1.99兆円。トランプ就任前のベースライン。
- 2017年度: 売上高29.4兆円、営業利益2.4兆円。減税や米国販売増で成長。
- 2018年度: 売上高30.2兆円、営業利益2.47兆円。貿易戦争の影響は軽微で堅調。
- 2019年度: 売上高29.9兆円、営業利益2.44兆円。コロナ初期の影響で微減。
- 2020年度(2020.4~2021.3): 売上高27.2兆円、営業利益2.2兆円。コロナで打撃も回復力示す。
- 総括: 売上高は30兆円前後で安定、営業利益も2兆円以上を維持。トランプ政策の恩恵(減税)とリスク(関税)を両方吸収。
ホンダ
- 2016年度: 売上高14.0兆円、営業利益8400億円。北米中心のビジネス。
- 2017年度: 売上高15.4兆円、営業利益8330億円。販売増もコスト増で利益横ばい。
- 2018年度: 売上高15.9兆円、営業利益7260億円。貿易摩擦で利益圧迫。
- 2019年度: 売上高14.9兆円、営業利益6340億円。コロナで大幅減益。
- 2020年度: 売上高13.2兆円、営業利益6600億円。回復もトヨタほど強くない。
- 総括: 売上高は15兆円前後で推移するが、利益は変動が大きく、コロナ禍での打撃が顕著。
比較: トヨタは規模と利益の安定性が際立ち、ホンダは北米市場への依存から変動が大きい。トランプの関税(鉄鋼・アルミなど)は両社にコスト増をもたらしたが、トヨタの方が影響を抑えた。
3. 配当の状況
両社は株主還元に積極的で、配当は業績と連動しつつも安定傾向。
トヨタ自動車
- 2016年度: 年間配当210円(中間100円、期末110円)。
- 2017年度: 220円(中間110円、期末110円)。業績好調で増配。
- 2018年度: 220円。横ばい維持。
- 2019年度: 220円。コロナ影響下でも維持。
- 2020年度: 240円(中間120円、期末120円)。回復見込みで増配。
- 総括: 1期目を通じて200円以上を維持し、増配傾向。配当性向は30%前後で安定。
ホンダ
- 2016年度: 年間配当88円(中間44円、期末44円)。
- 2017年度: 92円(中間46円、期末46円)。微増。
- 2018年度: 108円(中間54円、期末54円)。積極増配。
- 2019年度: 112円。コロナ下でも維持。
- 2020年度: 82円(中間28円、期末54円)。コロナで減配。
- 総括: 増配基調だったが、コロナで一時減配。配当性向は20~30%で推移。
比較: トヨタは高水準で安定、ホンダは業績変動を反映しつつも株主還元を意識。
4. トランプ政権1期目の影響
- プラス面: 減税・雇用法(2017年)で米国市場が活性化し、両社の販売台数が増加。特にトヨタはSUVやピックアップトラックの需要で恩恵。
- マイナス面: 鉄鋼・アルミニウム関税(2018年)でコスト増。米中貿易戦争でサプライチェーンが混乱し、ホンダの北米生産に影響。
- コロナの特殊要因: 2020年のパンデミックはトランプ政策とは別だが、株価と業績に大きな下押し圧力。
まとめ
- 株価: トヨタは5,500~8,000円、ホンダは2,200~3,600円で推移。トヨタの方が安定感あり。
- 業績: トヨタは売上30兆円・利益2兆円規模で堅調。ホンダは売上15兆円・利益6000~8000億円で変動大。
- 配当: トヨタは200~240円で増配基調、ホンダは80~112円でコロナ減配も回復。
注意
トランプ政権1期目と2期目では、金利と景気の状態が違います。
総合的な違いと背景
- 金利: 1期目は緩和的な金融環境への移行が特徴だったが、2期目はインフレと経済の強さで金利が高止まり。FRBとの対立も焦点。
- 景気: 1期目は政策で景気を押し上げたが、2期目は強い経済を継承しつつ、関税や混乱で減速リスクが拡大。
背景
- 1期目: 比較的安定した世界経済の中で、減税や規制緩和が効果を発揮。ただし、貿易戦争で波乱も。
- 2期目: コロナ後の回復が一段落し、インフレや地政学リスクが高い中でスタート。関税政策の規模と予測不可能性が1期目以上に市場を揺さぶっている。
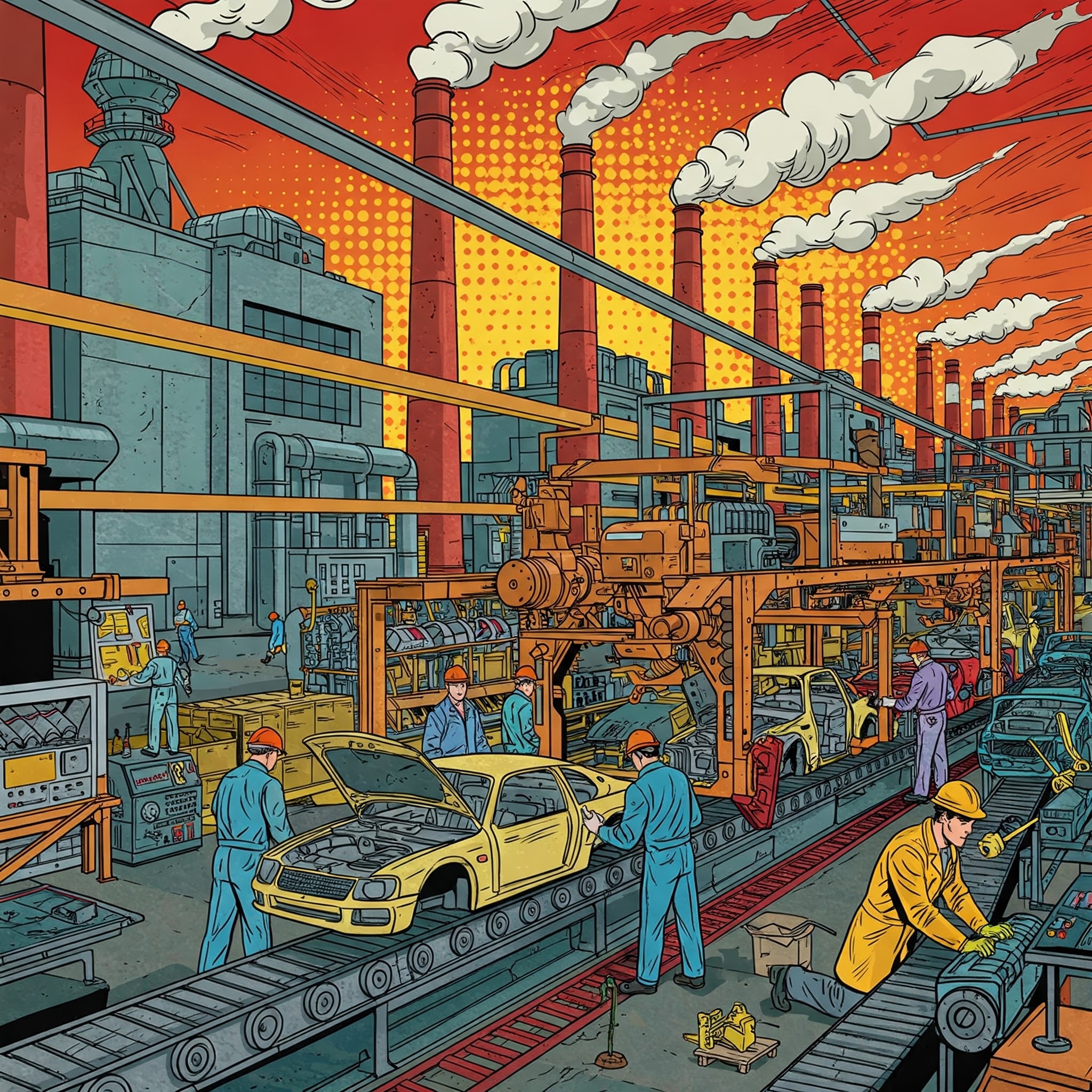
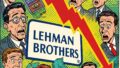

コメント